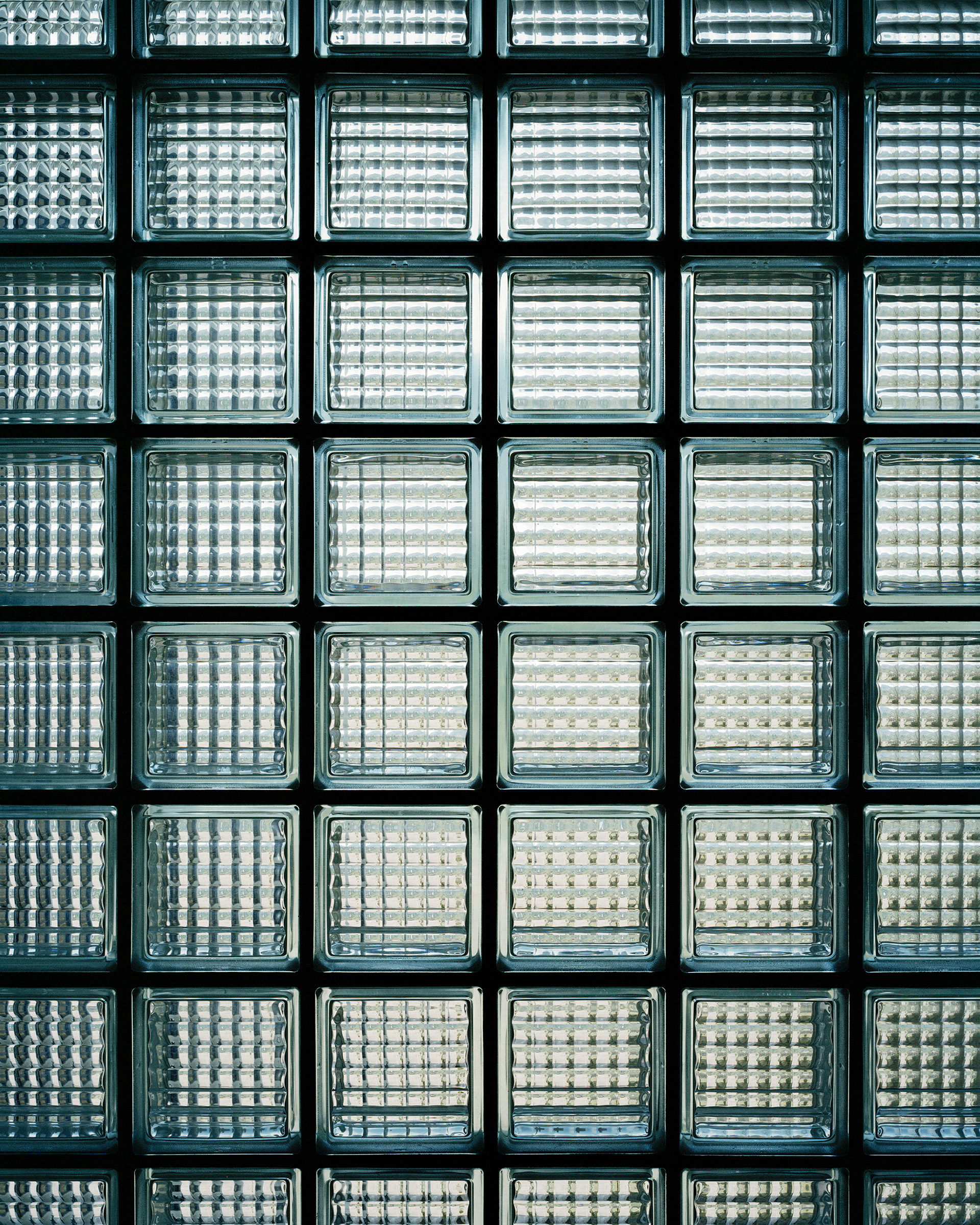「Voice(s)についての覚書き」
長野県信濃美術館は1966年に開館した。半世紀を経て、その本館は美術館としての役目を終えた。残雪の土地で光に照らされるその姿を、もはや見ることはできない。
指先を悴ませる12月の雨の中で見上げた屋根を、重機が挾み壊す。そのとき、コンクリートのなかの鉄骨が軋みをあげることを、わたしははじめて知った。足を運ぶその度に建物の姿は小さくなっていき、手元に残る像の量は、僅かずつであっても増えていく。
2017年の春、日が暮れ始めたころに屋根の上に登ったことがある。HPシェルという工法で造られたその場所は、離れて見れば滑らかな曲線を描き、この建物の特徴的なシルエットを形成していた。わたしの立つ位置からは、太陽が山の稜線に落ちてゆく姿が見え、間もなく翳り消えゆくその光によって、屋根の肌理が逆撫でられたように立ち上がる。夕日のなかで、表面をおおう傷や隆起は、その場所を交換可能な、機能としての屋根に還元することを拒んでいるようだった。自らの皮膚のように、傷跡を辿れば、きっと或るときを想い描くことができる。わたしもこの屋根も、時を重ねてきた存在として、ともに光の中に立っている。別れ難く時間と光によって織られている。
(距離を置いてみれば一枚の平らかな布であるのだが、その一部を注視すれば、そこには複雑に絡み合う糸たちの姿がある。均質に繰り返されているようなその細部の連なりは、わたしのまなざしの限界を超えたところで、無数に異なった様をしているのだろう)
それが在ったと言うとき、一つの風の中で、わたしが在ったと同時に発声すること。